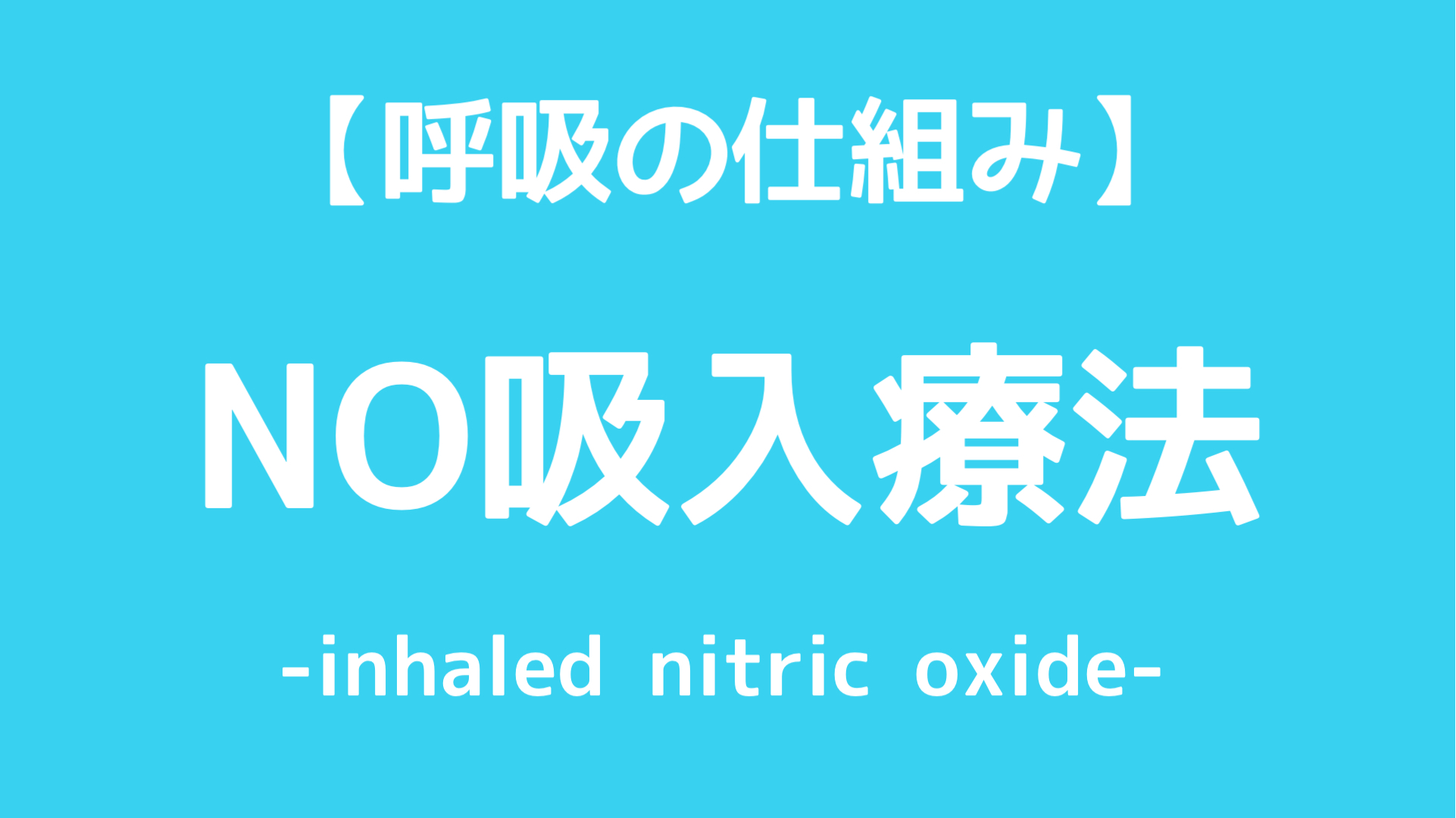NO吸入療法は、NO(一酸化窒素)を吸入させることで肺血管を選択的に拡張させる治療法です。
肺高血圧症などに適応がありますが、窒素ガスを直接吸入させますので注意点も多いです。
今回はそんなNO吸入療法について、治療の基礎と看護のポイントなどについて解説します。
目次
NO吸入療法とは
NO(一酸化窒素)吸入療法とは、平滑筋拡張作用のあるNOガスを人工呼吸器回路などに流し込み、肺に直接吸入させる治療法です。
NOガスの半減期は数秒と非常に短いので、肺血管のみに選択的に作用します。
全身の血管が拡張してしまうと血圧の低下が起こりますが、血管拡張作用が肺血管のみに限定されるので、全身循環に影響を与えず血圧低下は起こりにくいとされています。
肺高血圧症や、肺高血圧が要因となってしまっている低酸素性の呼吸不全、新生児遷延(せんえん)性肺高血圧症などに対して肺血管抵抗を下げる目的で用いられます。
NO吸入療法の適応
NO吸入療法導入当時は新生児の肺高血圧症を伴う低酸素性呼吸不全に対してのみ適応となっていました。
そこから現在では新生児〜成人までの全年齢において、心臓手術の周術期における肺高血圧症に対しても適応となりました。
しかし肺高血圧症であっても心臓手術周術期ではない場合に関しては未だ適応がなく、肺高血圧症治療ガイドラインにおいてもハッキリと明記されていないのが現状です。
特に成人症例において、心臓手術周術期ではないけれど重度の肺高血圧症により治療に難渋している症例は多々あります。
今後、こういった心臓手術関連以外での肺高血圧症の治療として、NO吸入療法が適応となる事に期待です。
※ある方のご意見として、成人肺高血圧症例では血管のリモデリング(病態の進行・繊維化)が進行して、NO吸入療法の効果は限定される場合も多いそうです。
NO吸入療法の方法
アイノフローDS
現在、NO吸入療法の代表的な方法としてアイノフローDSという装置を用います。
これは医療用NOガスボンベを搭載した装置で、NOガス回路を人工呼吸器の吸気側に接続し患者に吸入させます。
人工呼吸管理をされている患者であっても、自発呼吸の有無やその時の呼吸状態によって換気量は変動します。
換気量が変動している環境下でNOガスの投与量が一定だと、吸入されるガス濃度は一定ではなくなってしまいますよね。
アイノフローDSでは、人工呼吸器の吸気流量を検知してそれに応じたNOガスを供給してくれる様に制御されていますので、患者が吸入するNO濃度は基本的に一定です。
さらにアイノフローDSは人工呼吸器吸気側回路の患者口元付近のガスを常時サンプリングしているので、実際に患者が吸入しているNO濃度をモニターでひと目で確認できます。

工業用NOガスボンベ
前述した通り、成人の心臓手術症例以外での医療用NOガスの使用は保険適応となっていません。
しかし他に手段のない重篤な肺高血圧症の治療において、NOガス吸入による肺血管拡張効果に期待し、工業用のNOガスボンベ(窒素バランス80ppmに調整充填、充填圧120kgf/cm2、ねずみ色)を使用する事があります。
これも人工呼吸器の吸気側回路にNOガスを混入させ、患者に吸入させます。

NO吸入療法の看護のポイント
吸入NO濃度をチェック
NO吸入療法は、吸入させるNOガスの濃度をしっかりと管理する必要があります。
多くの場合、吸入NO濃度を10〜20ppmで維持します。
先程紹介したアイノフローDSでは、前述した通りに吸入ガスを常時サンプリングしているので、リアルタイムで確認ができる上に調整が簡単です。
ちなみにアイノフローDSでは、吸入濃度を20ppmで開始し、開始後4時間は20ppmを維持することを推奨しています。
一方で工業用NOガスボンベの場合は、人工呼吸器の吸気流量とNOガス流量から吸入NOガス濃度を計算しなければなりません。
バイタルサインの変化
NO吸入療法を選択するということは、前提として重症な症例であり、Aラインはもちろんスワンガンツカテーテルなどによって、様々な圧がモニターされていると思います。
NOガスを吸入するとバイタルが大きく変化するのでしっかり観察しましょう。
NOガス吸入の効果により肺血管が拡張されると、肺動脈圧(PAP)は減少、併せて中心静脈圧(CVP)も減少します。
また肺への血流が増えるので、肺のガス交換能に問題がなければ肺脈血酸素飽和度(SpO2)が上昇します。
循環動態が良くなれば収縮期血圧も上昇し、尿量の増加にも期待できます。
逆にNO吸入を開始してもバイタルサインが改善傾向に変化しない場合は、吸入NOガス濃度を調整する必要があるので、主治医にアセスメントできる様にしっかり観察しましょう。

NO吸入療法の合併症と注意点
PHクライシス
NO吸入療法では、水に溶けたNOが微量ですが硝酸や亜硝酸を発生させ、これが肺高血圧クライシス(PH crisis)と呼ばれる発作を引き起こす可能性があります。
PHクライシスでは、さまざまな刺激が原因となって肺血管抵抗が急上昇し、低酸素血症・血圧低下・心停止に発展する場合もある極めて危険な合併症です。
NO吸入療法中に限らずですが、人工呼吸回路内の結露をなるべく予防するための空調管理や適切な鎮静管理、慎重な気管内吸引を行うことで軽減できると考えられます。
NO2の生成
NOガス(一酸化窒素)は酸素と結合すると、NO2(二酸化窒素)やNO3と言った窒素化合物(NOX)になります。
これは車の排気ガスと同じ様な物質であり、大量に吸い込むことで呼吸器障害を引き起こす危険な物質となります。
NO吸入療法を考慮している患者というのは、前提として肺血管抵抗が高くて困っている患者です。
なのでNO吸入療法を始める前から、少しでも肺血管抵抗を下げるために人工呼吸器の酸素は通常よりも高濃度に設定されているはずです。

そんな高濃度の酸素が流れている人工呼吸器回路にNOガスを流すと言うことは、NO2が発生しやすい環境になっていると言えます。
その事を認識せずにNOと一緒にNO2も吸入させ続けてしまうと、逆に呼吸器障害を引き起こしてしまう可能性があります。
この事に注意してNO吸入療法を行う場合にはNO濃度と同時にNO2濃度も測定しましょう。
NO吸入療法におけるNO2の許容濃度は3〜5ppm以下とされています。
NOガス管理システム装置であるアイノフローDSでは、モニター画面にて、NO、NO2、に加え、O2濃度も常時監視する事ができます。(1枚目の写真参照)
メトヘモグロビン血症
NOは血中でヘモグロビンと結合しますが、ニトロシルヘモグロビンという物質に変化する事でこれを不活化します。
しかしこのニトロシルヘモグロビンは、さらに血中の酸素と結合する事で、メトヘモグロビン(Met Hb)という物質に変化します。
メトヘモグロビンには酸素運搬能はないので注意が必要です。
メトヘモグロビンの正常値は1〜2%とされ、10%以下では症状なし、15〜20%を超えてくると呼吸困難やチアノーゼの出現、脳虚血を引き起こすとも言われています。
メトヘモグロビンは血ガス測定装置で計測可能なので、NO吸入療法を行なっている場合は採血にて定期的に確認しましょう。
医療従事者への暴露
NO吸入療法を行なっている場合、上記の通り患者に対するNO2の生成とメトヘモグロビン血症が問題となります。
しかしこれは患者に対してだけではなく、医療従事者に対しても起こる可能性があります。
NO吸入療法を行なっている病室やベッドサイドでは、患者の呼気に含まれるNOやNO2、または回路やチューブの接続時などに漏れたNOが環境下の酸素と結合して生成されたNO2が充満している可能性があります。
数十年前のNO吸入療法が導入され始めた初期の頃では、患者に装着された人工呼吸器回路の呼気弁周囲のNO2濃度を測定したところ、NO2 2.1〜5.2ppmが検出されたとの報告があります。
この様な環境下で働いていては、医療従事者にも体調面で影響が出てもおかしくありません。

現在ではアイノフロー使用下の呼気の大気開放で環境に影響が出ていない事が確認され、薬事承認も降りていますので安心です。
工業用ボンベの場合でも呼気側にフィルター + 吸着剤を備える事で環境への影響は無いと考えられ、有害事象の報告もありません。
ですが万が一NO吸入療法に関わり何らかの症状が出る場合は、慎重に対処する必要があります。
※日本産業衛生学会の勧告では、環境下でのNO2の許容濃度は5ppmとされ、公害対策基本法での大気一般環境におけるNO2濃度の環境基準は0.04〜0.06ppmとしています。
※アメリカの国立労働安全衛生研究所(NIOSH)では、上限1ppm未満にとどめるように推奨されています。
まとめ
【概要】
・NO吸入療法は、NOガスを人工呼吸器回路などに流し込み換気させる事で肺に直接吸入させる治療法。
・NOガスの半減期は数秒と非常に短く、全身血管に影響を及ぼす事なく肺血管のみに作用する。
【適応】
・新生児の肺高血圧症を伴う低酸素性呼吸不全
・心臓手術の周術期における肺高血圧症(全年齢対象)
※心臓手術の周術期以外の肺高血圧症に対しても期待したい
【方法】
・アイノフローDS
・工業用NOボンベ
【看護のポイント】
・吸入NOガス濃度の維持、変化
・吸入NO2濃度の監視
・バイタルサインの変化
【合併症】
・PHクライシス
・NO2の生成
・メトヘモグロビン血症
・医療従事者への暴露