ECMO(PCPS)は人工肺によってガス交換を行い、ポンプによって循環を補助する強力な補助循環装置です。
ですがこの強力な補助循環にもリスクがあります。
ここではECMO(PCPS)を管理する上で高確率で発生するトラブルの1つ「プラズマリーク」についてその原因とメカニズム、対処法を解説していきます。
目次
ECMO(PCPS)とは
ECMOとはExtracorporeal Membrane Oxygenationのことを言い、日本語では「膜型人工肺による酸素化」と訳します。
送脱血管・血液回路・遠心ポンプ・人工肺で構成され、患者の呼吸と循環をサポートする強力な補助循環システムです。
日本では昔からPCPSと呼ばれてきましたが、最近ではECMOと呼ぶ施設が増えてきました。
施設や部署によって呼び方が違うとややこしいですが、やっている事は同じです。
人工肺について
ECMOシステムの要となるのが人工肺です。
人工肺とは、文字通り肺の機能を肩代わりして行う人工物です。
人工肺の内部で、患者の血液と壁配管から送られてきた酸素を触れ合わせることで、酸素の付与・二酸化炭素の排泄を行います。
人工肺をECMOを行う上で欠かせない構成品ですが、良いことばかりではありません。
ECMOの人工肺に起こるトラブルは代表的なものが2つあります。
①ウェットラング
②プラズマリーク
ウェットラングについては別の記事で解説していますので、参考にしてみて下さい。
プラズマリークとは
プラズマリークとは、血液の成分の1つであるプラズマ(血漿)が、人工肺を通して外にリーク(漏れる)する現象です。
文字通り、血漿リークとも言います。
<プラズマリーク1>

<プラズマリーク2>

写真の様にプラズマリークが発生すると、人工肺のガス出口から黄色い泡の様なものが浸出してきます。
この黄色の成分が血漿です。
ウェットラングでも人工肺に液体が付着しますが、この場合は結露による水滴なので、透明色です。
この様に色の違いからもウェットラングとプラズマリークを判別することが出来ます。
プラズマリークが起こる原因
結論から言うとプラズマリークが起こる原因は、人工肺の長期間の使用による膜の劣化です。
人工肺は、内部で血液の通り道と酸素などのガスの通り道が膜によって隔てられています。
この膜はガス交換をするための孔が開いているのですが、膜の素材は疎水性で水分をはじく様に出来ています。
血漿も液体としての表面張力が働いているので、この2つの作用により通常では血漿が漏れ出てくる事はありません。

しかし人工肺の疎水性は長期間の使用により徐々に劣化してきます。
血漿の表面張力で留めきれなくなった時、膜の外に血漿がリークしてきます。

私の経験から言うと、長くて1〜2週間、早い時には3〜4日でプラズマリークが発生している印象です。
プラズマリークが発生すると、ガス交換効率も悪くなります。
プラズマリークが起こるとどうなるのか
次にプラズマリークが発生すると、どんな困ることが起こるのか考えてみます。
人工肺ガス交換効率が低下する
前述した様にプラズマリークが発生するとガス交換効率が著しく低下します。
ECMO導入中は、呼吸管理は人工肺に頼っている部分が大きいので、こうなるとSpO2の低下・PaO2の低下・PaCO2の上昇などの変化が見られます。
患者の血漿成分の喪失
血漿とは血液の中の血球意外の成分です。
この中には浸透圧維持に関わるアルブミン、免疫機能維持に関与するグロブリン、止血機能の役割のある凝固因子などが含まれています。
プラズマリークによってこれらの成分が失われ続けると、浸透圧低下・免疫の低下・出血傾向などが起こり得ます。
医療従事者への感染のリスク
covid-19による呼吸機能の低下により多くの症例でECMOが導入されています。
プラズマリークの成分中に新型コロナウィルスが潜んでいる可能性を完全に否定する事は出来ません。
現在のところ、プラズマリークによる医療従事者への感染は報告されていませんが、注意する様に日本COVID-19対策ECMOnetより注意喚起が出されています。
プラズマリークの対処法
プラズマリークの原因は、劣化による膜の疎水性の消失でした。
これはウェットラングの様にO2フラッシュをしたからと言って改善するものではありません。
プラズマリークが見られた時の対処法は人工肺の交換です。
これしかありません。
人工肺を新品の状態からリスタートし、患者の状態が改善してくるまで仕切り直しましょう。
人工肺だけを交換する方法もありますが、人工肺のポジションや遠心ポンプまでの距離などの関係から、血液回路・遠心ポンプを含む全てをまるごと交換する方法がより無難だと思います。
別の記事でプラズマリークの動画を公開しているので、イメージの参考にしてみて下さい。

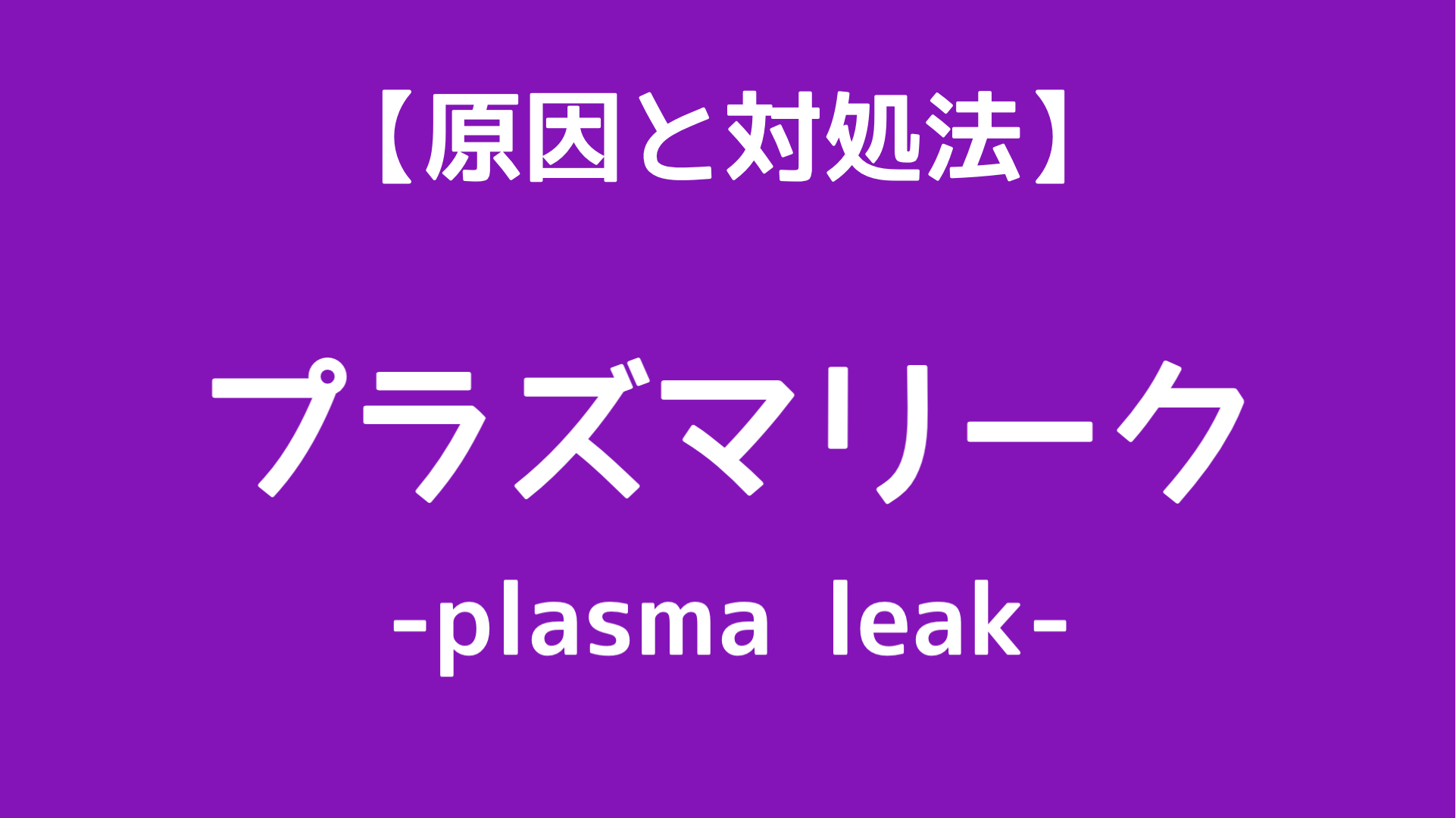




















コメントを残す