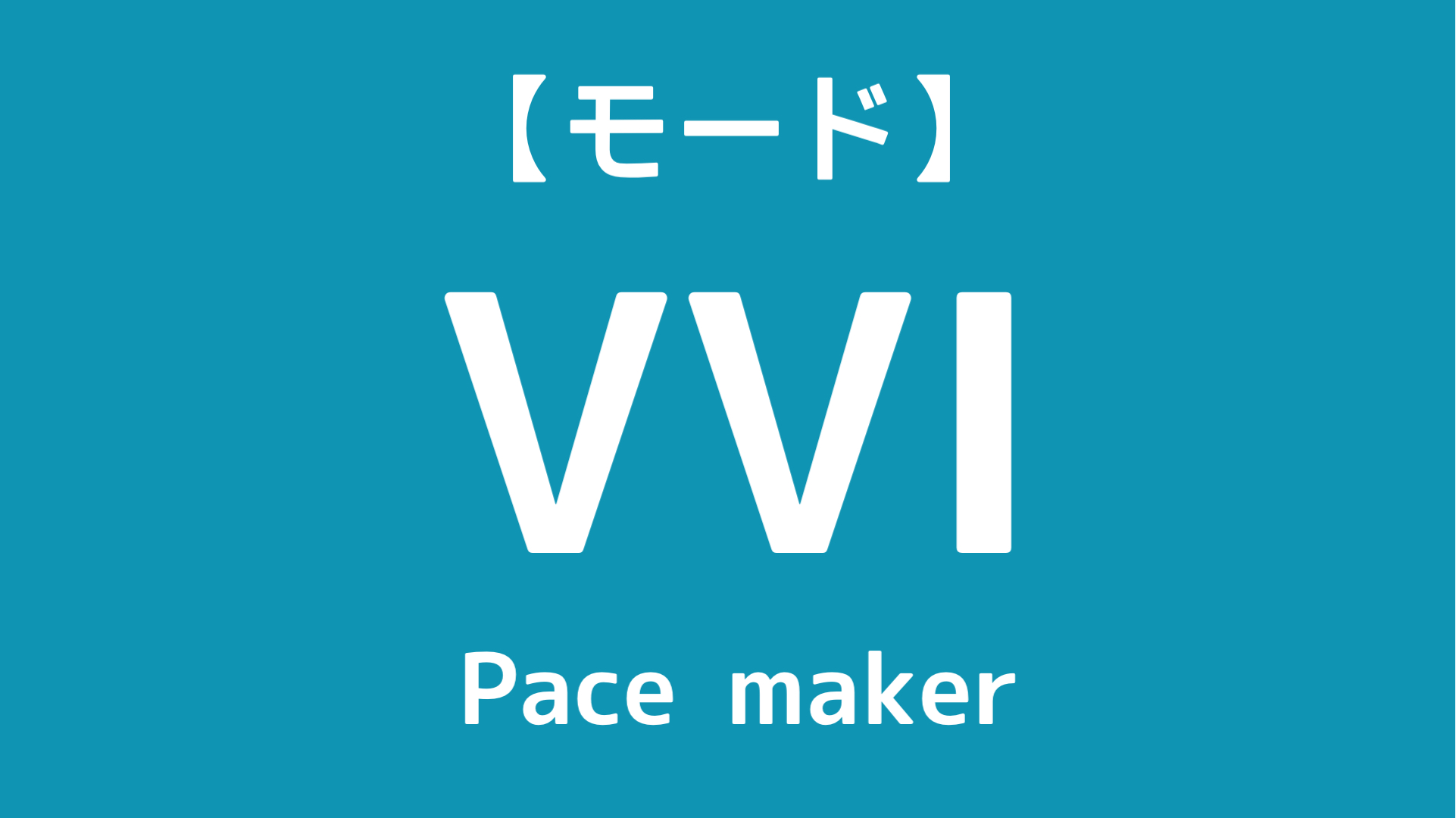ペースメーカーは心拍数がゆっくりになる病気(徐脈性不整脈)に対して導入され、電気刺激(ペーシング)によって心臓を動かすことで心拍数が低下するのを防ぐデバイスです。
最近のペースメーカーはたくさんの種類やモードを搭載したモデルがありますが、今回はペースメーカーの基礎と、最も基本的なモード【VVIモード】についてイラストを多数用いて解説したいと思います。
目次
ペースメーカーの基礎
概要


① 本体
② リード線
の2つで構成されています。
※最近ではリードレスペースメーカーと呼ばれる、文字通りリードの無いタイプのものもあります。
本体には電気刺激を出力するための『電池』と、パターンに応じて電気刺激を出したり、あるいは電気刺激を出さずに抑制したりといった、ペースメーカー1拍1拍の動作を制御する『制御システム』が入っています。
本体は基本的には前胸部に植え込まれる事が多いです。
リード線は先端を心臓の内壁に留置し、これをペースメーカー本体と接続する事で電気刺激を心臓まで伝えます。
リード線は目的に応じて1本だけの場合もありますし、2本接続される場合もあります。
それによって使えるモードが変わってきます。
適応
不整脈非薬物治療ガイドラインによると、ペースメーカーの適応は、
・房室ブロック
・二枝および三枝ブロック
・洞不全症候群
・徐脈性心房細動
・過敏性頸動脈洞症候群、反射性失神
・閉塞性肥大型心筋症
と書かれています。(詳細はガイドライン本文を参照)
たくさんあって覚えにくいですが、要となるのは、徐脈性の不整脈(心拍数がゆっくりになってしまう病気)に対して適応となるのがほとんど、という事です。
ペースメーカーは患者さんの心拍数が低下した時、設定した心拍数を担保する様に電気刺激を送ります。
つまり徐脈性の不整脈発作のせいで心拍数が極端に低下し、めまいや失神という症状が出ていた患者さんはペースメーカーを導入することで心拍数が低下することはなくなります。
これにより患者さんのQOLは格段に向上します。
ペースメーカーの種類
ペースメーカーには大きく分けて2種類のスタイルがあります。それは、
① 恒久的ペースメーカー
② 一時的ペースメーカー
の2つです。
これらは目的や状況によって使い分けられます。
恒久的ペースメーカー

『こうきゅうてき』と読みます。
恒久とは、『永久』とか『ずっと』などと言う意味があります。
ペースメーカーの世界では、体内に植え込む事で『永久的』に使用できるもの、と言う意味で使われ分類される言葉です。
(実際には電池交換など必要であり、永久的に使用できる訳では無いので少し大袈裟な気もしますが・・・。)

恒久的ペースメーカーは、『植え込み式ペースメーカー』や『永久式ペースメーカー』と呼ばれることもあります。
特に指示や注意書きなど無く『ペースメーカー』とだけ書かれている場合、この恒久的(植え込み式)ペースメーカーの事を指している場合がほとんどです。
近年、リードレスペースメーカーと言うものが登場しましたが、これも体内に植え込まれるものなので恒久的ペースメーカーに分類されます。
一時的ペースメーカー

一時的ペースメーカーは術中や術後など一時的に心拍数が低下する恐れがある場合にバックアップ用として導入しておくものになります。
本体を体内には植え込まず、内頸静脈や大腿静脈から挿入したテンポラリーリード(一時的リード)だけを心臓の内壁に留置します。
そしてリード線の反対側を体外で一時的ペースメーカー本体と接続する事で、ペーシングシステムを確立するのが一時的ペースメーカーのスタイルです。
術中・術後の経過を診て、心拍数の低下はもう起こらないと判断されたらリード線を抜去します。
もしも一時的ペースメーカーの電気刺激に依存し、ペースメーカーなしでは退院が望めない場合などは、そのまま恒久的ペースメーカーの植え込みになったりもします。
一時的ペースメーカーは英語読みで『テンポラリーペースメーカー』とも呼ばれます。
他にも『体外式ペースメーカー』や『外付けペースメーカー』など、様々な名前で呼ばれる事があるので混乱しないようにしましょう。
ちなみに恒久的ペースメーカーの英語読みは『パーマネントペースメーカー』です。
(一時的ペースメーカーには体表に貼った電極を用いた経皮ペーシングと言う方法がありますが、かなりの痛みを伴う上にペーシングの確実な効果を判定することが難しく使用されることは稀です。)
テンポラリーペースメーカーは、使い方を誤ると危険な事が起こり得るので注意が必要です。
実際に当院でも過去にインシデントが発生しました。
その時のことについてコチラの記事にまとめていますので、良かったら参考にどうぞ。
VVIモードについて
ここからはペースメーカーのモードにおいて最も基本的なモード【VVI】について、補足事項も交えながら解説していきます。
NBGコード
ペースメーカーの動作はNBGコードと呼ばれる3文字(たまに4文字にもなる)のアルファベットで表されます。
1文字目はペーシング(刺激)部位、2文字目はセンシング(感知)部位、3文字目は動作様式(どの様にペーシングするのか、またはペーシングしないのか)を表します。
そしてアルファベットは、ペーシング・センシング部位では、A、V、O、の4パターンで示され、それぞれ、
A:心房(Atrium)
V:心室(Ventricle)
D:両方(Dual)
O:刺激しない
を表します。
動作様式では、I、T、D、Oの4パターンで示され、それぞれ、
I:抑制(Inhibit)
T:同期(Trigger)
D:両方(Dual)
O:固定
を表します。
つまりVVIモードは、
・ペーシング(刺激)部位は心室、
・センシング(感知)部位も心室、
・動作様式はインヒビット(抑制)
ということになりますね。
これを分かりやすくまとめると次のイラストの様になります。

4文字目には『R』という文字が付くことがあります。
Rは反応(Response)を意味しており、患者さんの身体活動量に応じてペーシングレートを変化させる設定になります。
NBGコードの4文字目は基本的にペースメーカーのオプション機能だと思ってOKです。
例えばVVIモードに4文字目のオプションを付けると、『VVIR』と言うモードになります。
これについては次回、解説しようと思います。
ペースメーカーのモードは数多くありますが、臨床的によく使用されている代表的なモードはAAI、VVI、DDD、VDDの4つです。
今回はVVIモードのみの解説ですが、余裕があればコレらのモードの動作についても覚えておくといいかも知れません。
方法
VVIモードは心室のみをターゲットとして動作するモードです。
なのでVVIモードを使用するためには、心室にリード線が1本入っていれば使用することができます。
リード線は1本でペーシング(刺激)とセンシング(感知)を行うことができるので、VVIモードは最も分かりやすいモードと言えます。
一時的(テンポラリー)ペースメーカーを用いてVVIモードを使用する際も、心室へテンポラリーリード線が1本入っていれば、あとは体外で本体と接続すればOKです。

動作
ペースメーカーには様々なモードが搭載されています。
どのモードに対しても共通して言えることがあり、それは
「ペースメーカーはどんなモードであっても、動作様式が『抑制』であっても、基本的にはペーシング刺激を出そうとするもの」と言うことと、
「ペースメーカーのモードを考える時は、必ず『ペーシングレート』もセットで考える」と言うことです。
(※ペーシングレートとは、ペースメーカーに設定する心拍数のことです。)

VVIモードは、ペーシング(刺激)部位は心室、センシンング(感知)部位も心室です。
そして動作様式はインヒビット(抑制)です。
抑制と言うことはペーシング刺激は全て抑制されるのではないかと思いがちですが、そうではありません。
ペースメーカーはどんなモードであっても基本的にはペーシング刺激を出そうとするものです。
つまりVVIモードであってもペースメーカー本体は常にペーシング刺激を「出そう出そう」としているのですが、設定したペーシングレートよりも自己心拍数が多い時にこれが抑制されます。
VVIモードの【抑制】とは、こういった意味での抑制となります。
まとめると、VVIモードは、
・ペーシング(刺激)部位は心室。
・センシング(感知)部位も心室。
・自己心拍数 > 設定したペーシングレートの場合:ペーシングは抑制(Inhibit)される。
・自己心拍数 < 設定したペーシングレートの場合:抑制はされず、ペースメーカーの基本性能としてのペーシング刺激が出力される。
となります。
この考え方は、他のモードを考える時にも役に立ちます。

例1.【自己心拍数 > ペーシングレート】の場合
ある患者さんにペースメーカーが導入されており、モードはVVI、ペーシングレートは50回/分の設定です。
状態(あるいは心電図モニター)を確認した時、患者さんの心拍数は60回/分でした。
これはつまり患者さんの自己心拍数が設定されたペーシングレートよりも多いので、ペースメーカーは基本性能としてペーシング刺激を出したいんだけど抑制されていると言う状態となっています。

イラストの『センシング』について理解するにはコチラの記事のイラストを参考にしてみるといいと思います。
例2.【自己心拍数 < ペーシングレート】の場合
先程の患者さんがあるタイミングで、心電図モニターの心拍数が50回/分となりました。
モニターにはペーシング刺激が出力された事を表すペーシングスパイクの波形も確認できます。
これはつまり患者さんの自己心拍数が低下し、設定されたペーシングレートの方が多くなったので『抑制』の動作は行われず、ペースメーカーの基本性能としてのペーシング刺激が出力された、と言う事を意味しています。

まとめ
●ペースメーカーの基礎として、
・ペースメーカーは、①本体と ②リード線で構成される。
・本体の中には、①電池と ②制御システムが入っている。
・ペースメーカーの適応は、徐脈性の不整脈がほとんど。
・ペースメーカーの種類には、①恒久的ペースメーカーと ②一時的ペースメーカーがある。
●VVIモードにおいて
・NBGコードでは、ペーシング(刺激)部位は心室。センシング(感知)部位も心室。動作様式はインヒビット(抑制)。
・心室にリード線を1本留置すれば使用できる。
・モードに限らずペースメーカーの基本性能として、ペーシング刺激を出そうとする。
・ペースメーカーのモードを考える時は、必ず『ペーシングレート』もセットで考える。
・自己心拍数 > 設定したペーシングレートの場合:ペーシングは抑制(Inhibit)される。
・自己心拍数 < 設定したペーシングレートの場合:抑制はされず、ペースメーカーの基本性能としてのペーシング刺激が出力される。

最後に
私は職場でもよく他職種の方からペースメーカーやモードのことについて質問を受けます。
ここまで私の知っていることを感覚的に分かりやすく説明したつもりですが、もしかすると余計に混乱させてしまったかも知れません。
私の話し言葉で分かりにくい場合は、やはり自分にあった教科書を読み込むのがイチバンだと思います。
次の教科書は私がペースメーカーに関わり始めた頃に読んでいた教科書で、現在もたまに開いて復習したりしてます。
ペースメーカーのことがまだよく分からない人、もっと詳しいことも知りたい人におすすめですので、是非一度読んでみてください。