SvO2(静脈血酸素飽和度)の正常値は75%です。
SvO2は組織の酸素需要量と酸素供給量のバランスを表し、循環動態の変化や感染兆候など様々な指標に用いる集中治療室では大切なモニタリング項目の1つとなります。
本来SvO2の測定は肺動脈カテーテルが必要であり、昔はその肺動脈カテーテルから定期的に採血を行い測定していました。
最近では光ファイバーモジュールを組み込んだ肺動脈カテーテル(スワンガンツカテーテル)を使用することで、採血を頻回に行わなくても連続してSvO2の値をモニターする事が可能となっています。
今回はSvO2とは何なのか? 正常値はいくらなのか?
そして「数字ばかりでなかなか覚えられない」、「覚えてもすぐに忘れちゃう」という方向けに、SvO2の覚え方とイメージについて解説します。
目次
SvO2とは
SvO2(エスブイオーツー)とは、Saturation(飽和度)Venous(静脈)Oxygen(酸素)の頭文字を繋げたもので、日本語で言うと静脈血酸素飽和度と言います。
SvO2は集中治療室では、先端が肺動脈に留置されるスワンガンツカテーテルを挿入することによって測定する事が可能となる検査項目です。
SvO2の値をモニタリングすることで、循環動態の変化、感染や炎症などの兆候を捉える事ができます。
結論から言うと、
・SvO2の値は75%
・SvO2の値が75%よりも低下している場合には、循環動態の悪化(心機能の低下)や感染・炎症を疑う
と考えます。(これについては下記の項目にてゆっくり解説することとします。)
教科書によってはSvO2を混合静脈血酸素飽和度と呼んでいるところもあります。
これは、スワンガンツカテーテルで測定されるSvO2は、正確には
①上大静脈
②下大静脈
③冠状静脈
から流れて来る3つの静脈血が混ざりあったものの事を言うので、「混合」と言い表しています。
測定しているものは同じものなので、呼び方はどちらでも問題ないです。
ただし厳密に言うと、混合静脈血酸素飽和度の場合はvの上に線を引き、Sv‾O2と表します。
読み方としてはエスブイバーオーツーと読みます。
SvO2とSaO2
SvO2に対してSaO2というものもあり、ついでにセットで覚えておくと良いかと思います。
SaO2は、静脈(venous)の「v」に対して動脈(artery)の「a」、つまり動脈血酸素飽和度の事を言います。
SaO2も酸素解離曲線を考える上で非常に重要となってくる項目です。
ちなみにSpO2も動脈血酸素飽和度の事を言いますが、これは特に脈拍パルス(pulse)の「p」、つまりパルスオキシメーターを用いた経皮的動脈血酸素飽和度を意味します。
SaO2は動脈血を採血し、血液ガス分析装置で直接測定した時の動脈血酸素飽和度の事です。
SaO2の正常値は100%です。
<ちょっと小まとめ>
SvO2=静脈血酸素飽和度(正常値:75%)
Sv‾O2=混合静脈血酸素飽和度(正常値:75%)
SaO2=動脈血酸素飽和度(正常値:100%)
SpO2=経皮的動脈血酸素飽和度(正常値:100%)
SvO2の正常値
多くの教科書ではSvO2の正常値は68%〜77%程度と書かれているかと思います。
しかしこれだと中途半端で覚えにくいですよね。
ただでさえ集中治療室ではしっかり覚えておかなければならないモニタリング項目が多いので、初めのうちはなるべくシンプルに覚えておきましょう。
先ほどでも少し触れた通り、ここでは「SvO2の正常値は75%!」として覚えてもらおうと思います。
(もちろん私と同じ様にSvO2の正常値75%と明記している教科書もあります。)
これにはちゃんとした理由があって、75%の方が絶対に覚えやすく、イメージもし易いからなんです。
その理由を次からイラスト画像を駆使して説明していきます。
SvO2の正常値と考え方
SvO2の正常値は75%です。
これはヘモグロビンと酸素の関係を考えてみると簡単に計算する事が出来ます。
ヘモグロビンとは赤血球に含まれる成分で、肺で受け取った酸素を全身の組織へ送り届ける役割があります。
このヘモグロビンですが、1個につき酸素を掴む為の手が4つあるとイメージしてみて下さい。
手が4つあるので、血流に乗って肺を通過した時、その手には4つの酸素が掴まれています。

その後、心臓から全身の諸臓器に向けて拍出されたヘモグロビンは、組織に到着すると4つ持っている酸素のうち、1つだけを組織に受け渡します。
持っていた酸素の1/4を失い、残りの酸素の数が3/4となったヘモグロビンは毛細血管を経て静脈に還流します。

ポイントは、静脈にいるヘモグロビンが持っている酸素の数は3/4になっているという事。
3÷4=0.75 → 75%
ここでようやく75%という数字が出てきました。
これがSvO2の正常値が75%である事の証明になります。
その後も血液の循環は繰り返されます。
4つの手に3つの酸素を掴んでいるヘモグロビンは再び肺へと還流し、そこで1つの酸素を受け取り、4/4(=100%)となります。
これもSaO2の正常値が100%である事の証明になりますね。
まとめると、正常な生体では
① ヘモグロビンが肺で酸素を受け取り(4つの手に4つの酸素)、
② 組織で酸素を1つだけ受け渡す事で(1/4だけ酸素を渡す)、
③ 静脈へ向かうヘモグロビンは、酸素の持ち数が3/4になっている。
④ 3/4ということは0.75であり、つまりSvO2の値は75%になる。
⑤ その後ヘモグロビンは再び肺で酸素を1つだけ受け取り、4/4、つまりSaO2 100%となって組織に向かって拍出されていく。これが繰り返されていく。
この様に考えます。
ただしこれはあくまでSvO2の正常値を覚えやすくするための考え方です。
実際に集中治療室で患者さんのSvO2値を見た時、68%や77%という中途半端な数字が出ることも当然あります。
より正確なSvO2を計算できる式もありますが、ここでは簡単なイメージとして上記のことを覚えて下さい。
SvO2が低下するのはどんな時?
ではここからSvO2の値が低下している時、患者さんの身体の中で何が起こっているのかイメージしやすい様に説明していきます。
感染や発熱、炎症が起こっている
生体は感染を起こしている時、組織の代謝を亢進させ酸素消費量を増加させます。
組織が必要としている酸素の消量がいつもよりも増加している時に、いつも通りに4つの酸素を持ったヘモグロビンが組織に到着して1つの酸素を渡そうとした時、
組織は「今は感染中で酸素の消費量が上がっているから、たったの1コの酸素だけじゃあ足りないよ!」
と言って、ヘモグロビンが持つ4つの酸素を2つも3つも奪っていきます。
たくさんの酸素を取られたヘモグロビンが静脈に戻ってきた頃には、正常状態の時と比べて持っている酸素が少ないのでSvO2の値も低下します。

例えば静脈に戻ってきたヘモグロビンが酸素を2つしか持っていなかった場合、
2÷4=0.5 → 50%
よってSvO2が50%に近づく事がイメージできるかと思います。
心拍出量が低下している
心拍出量が低下している時もSvO2の値は低下します。
早い話が循環動態の悪化、心機能が低下している場合です。
ここで大切なのは、心拍出量とヘモグロビンの数が相関していると言う事です。
心拍出量が低下し、組織へ向けて送り出されるヘモグロビンの総数が低下していると、まるで少子高齢化の様に多くの組織を支えるヘモグロビン1つあたりの負担が相対的に増えます。
酸素を4つしか持っていないヘモグロビンがいつもよりも多くの酸素を納めなければならないので、先ほどと同様に静脈へ戻ってきたヘモグロビンが持つ酸素の数はいつもよりも少なくなりSvO2は低下します。

Hbが低下している
失血などによって、血中ヘモグロビン値が低下している場合でもSvO2の値は低下します。
これは例えば少子化をイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
少子化によりヘモグロビンの数が少なくなる事で、先ほどと同じ様に組織に対するヘモグロビン1つあたりの負担が増え、SvO2は低下します。
出血や貧血によりHbの値が低下していないかをチェックし、必要であれば輸血を考慮しましょう。
SvO2とcSvO2の違い
ここまでの解説ではずっと「SvO2」という言葉で説明してきました。
しかし皆さんの中には「cSvO2」という言葉を聞いたことがある方もおられるのではないでしょうか?
SvO2とcSvO2は厳密には区別されるべき項目ですが、実際の臨床ではほとんど同様の意味として使われてしまっています。
確かにSvO2とcSvO2の値にほとんど変わりがありませんが、この2つの正確な意味を知っておく事は大切だと思います。
前述している通りSvO2は混合静脈血酸素飽和度を意味し、上大静脈血、下大静脈血、冠状静脈血を混合した部位、つまり右心室〜肺動脈内の静脈血になります。
ここを正確に測定するためには肺動脈カテーテルが必要となります。
対してcSvO2は、Central Saturation Venous Oxygenの頭文字を繋げたもので、日本語では中心静脈血酸素飽和度と言います。
中心静脈とは体の中心に位置する静脈で、具体的には上大静脈または下大静脈のことを指します。
cSvO2を測定するにはCVカテからの採血で可能となり、この値には冠状静脈血は含まれません。
CVカテーテルの凡用さからcSvO2はSvO2の代用として使用されることが多いです。
しかし繰り返しになりますが、CVカテから採血したcSvO2には冠状静脈の値は含まれていませんので、SvO2とは若干の誤差があります。
具体的にはcSvO2の方が、7±4%ほど酸素飽和度が高いとされています。
<もう一度小まとめ>
SvO2=静脈血酸素飽和度(正常値:75%)
Sv‾O2=混合静脈血酸素飽和度(正常値:75%)
cSvO2=中心静脈血酸素飽和度(正常値:75%±@)
最後に
どうでしたか?
SvO2とヘモグロビンについてイメージできましたでしょうか?
SvO2は集中治療においてとっても役に立つモニタリング項目となるので、しっかりイメージを持って観察してみると良いと思います。
また紹介した様に、SvO2には似たような言葉が多いのでそれらの違いを知識として知っておくと便利です。
なお、ヘモグロビンが組織で酸素を受け渡す事に関しては酸素解離曲線を考える事が大切になってきます。
以下の記事でも解説していますので参考にしてみて下さい。

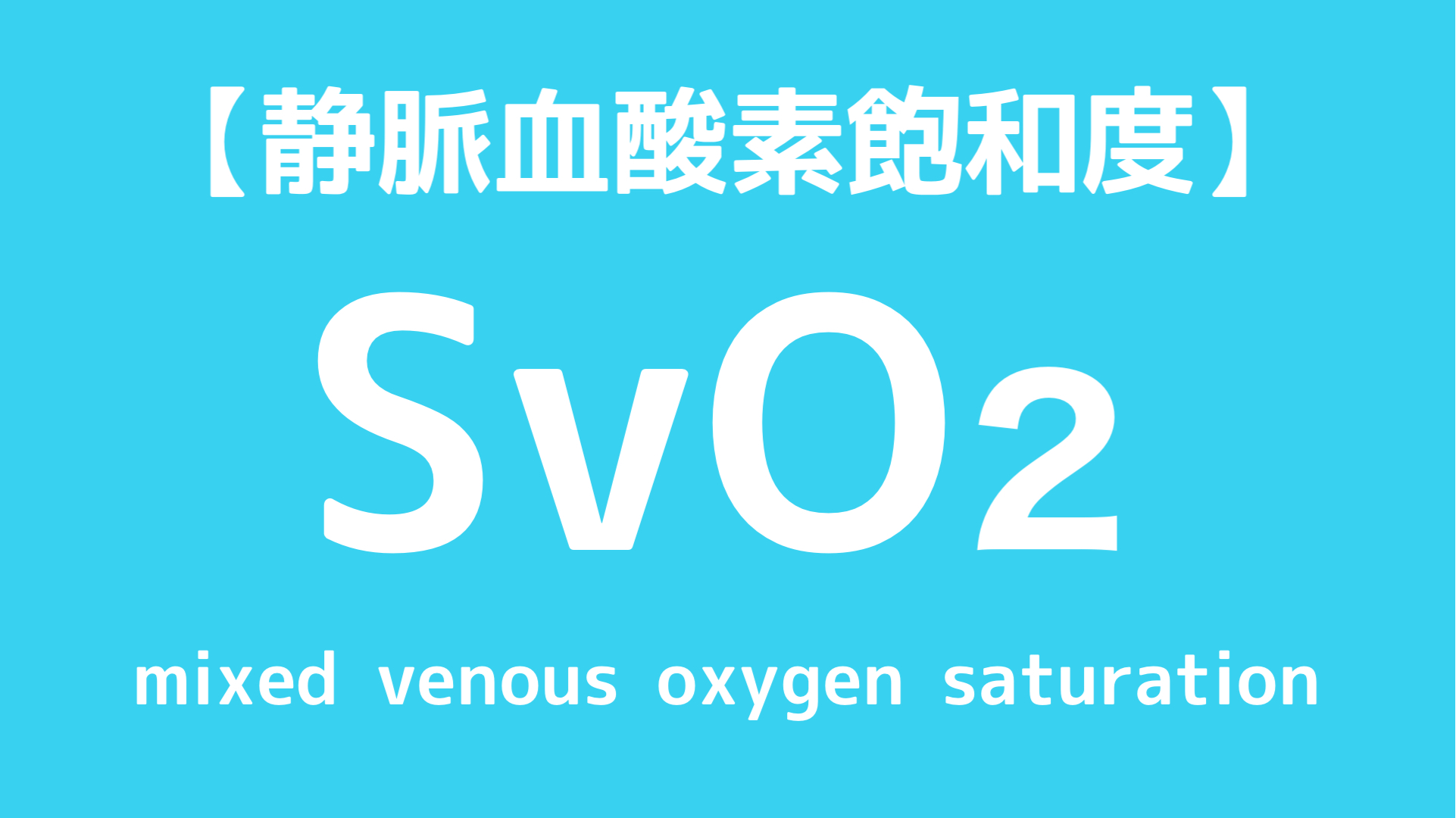





















初めまして。ICU看護師です。
いつも勉強させていただいています。
リクエストなのですが。
スワンガンツカテーテルの評価について教えていただきたいです。肺動脈圧の拡張期、収縮期のデータをどのように評価していくのかが、よくわかりません。
エクペラなど、補助循環を離脱した後、S-Gでは、
肺動脈圧の拡張期、収縮期の注意する変化など教えていただきたいです。
あとは、エクペラで、呼吸器とPCPSは、どのように設定しているのですか。
miwaさん、リクエストありがとうございます。
補助循環とスワンガンツの評価ですね!了解しました(^^)
ちょっと内容が濃いので、私自身勉強し直して、時間のある時にまとめを書いてみようと思います。