集中治療室に勤務していると、CHDF(持続的血液透析ろ過)の管理・看護の担当になる機会が多くあります。
CHDFの回路はとても複雑で、特に新人の頃には正直何に注意して診ればいいのか分からないと思います。
(私も新人の頃、本当にワケが分からなかったです。。。)
この記事ではCHDFの管理・看護に関する重要なポイントとその見方について解説します。
目次
CHDF看護のコツ
まずは回路図を理解してみよう

CHDFを仕組みを理解するためにはCHDFの回路を理解する必要があります。
ですが回路図を見てもらって分かるように、CHDFの回路はとっても複雑です。
ある程度経験を積めば何となくわかってくるものですが、初めのうちはワケが分からないと思います。
これを少しでも理解できる手助けになるように、CHDFをメイン回路とサイド回路に分けて、解説しようと思います。

コチラがCHDFのメインとなる血液回路です。
血液の流れを順番にまとめると、
① ブラッドアクセスから血液ポンプによって脱血する。
↓
② 血液ポンプの手前に「ピロー」と呼ばれる膨らんだ部分があり、脱血不良の有無をモニタリングしている。
↓
③ 途中で抗凝固薬が付加される。
↓
④ 血液は一度、Aチャンバーに貯められる。
⑤ Aチャンバーは装置内部の圧力計に繋がっており、ダイアライザーの入口圧をモニタリングしている。
↓
⑥ 血液はダイアライザーへ送られる。
↓
⑦ ダイアライザーから出た血液は一度、Vチャンバーに貯められる。
⑧ Vチャンバーも装置内部の圧力計に繋がっており、ここでは患者さんへの返血圧をモニタリングしている。
↓
⑨ ブラッドアクセスより、血液は患者へ返血される。
⑩ 途中で、間違って気泡を患者さんへ送ってしまうことを防止する為の気泡センサーがある。
この様な流れとなります。
ここまでが理解できたらCHDF回路の半分は理解できた様なものです!
では続いてサイド回路についても解説していきます。

サイド回路には、
・透析液回路
・濾液回路
・補液回路
の、3つがあります。
サイド回路のスタートは、装置に吊り下げた透析液(サブパックなど)です。
① 透析液ポンプによって、吊り下げた透析液をダイアライザーへ送る。
② 途中で透析液切れ対策の為の気泡センサーがある。
↓
③ 透析液はダイアライザーの内部を通って、半透膜を介して血液と触れ合うことで透析が行われる。
↓
④ 濾液ポンプによってダイアライザー内の濾過が行われる。
⑤ 濾液チャンバーも装置の内部の圧力計に繋がっており、ここでは濾過圧をモニタリングしている。
↓
⑥ 途中で、ダイアライザーの内部でトラブルが起こり漏血が起こってしまった時に早期発見する為の漏血センサーがある。
↓
⑦ 濾液は廃液処理される。
CHDFでは透析液を補液としても使用します。
⑧ 補液ポンプによって、吊り下げた透析液をVチャンバーへ送る。
⑨ 途中で補液切れ対策の為の気泡センサーがある。
↓
⑩ 補液はVチャンバーを介してメイン回路の血液と合流し、そのまま患者さんへ返血されていく。
サイド回路についてはこの様な流れとなります。
どうでしょう?こうやって2つに分けて考えてみるとわかりやすくないでしょうか?
CHDFの仕組みやシステムがわかりにくかったり、苦手意識の強い人は是非この様に考えてみて下さい。
患者 → 装置の順番で観る
さて回路の構成や流れが分かったところで、続いてはCHDF看護のコツとして「まずは患者を観て、次に装置を観る」ということをお伝えしようと思います。
先程の「メイン回路をみて、サイド回路をみる」と同じ容量です。
全部を一気に観ようとすると混乱してしまいますので、順番にみていく事がCHDFを看護・管理するコツだと思っています。
毎回同じ手順で確認していくことで見落としも失くしていけます。
では事項にて、患者側と装置側で具体的にどこを観ていけばいいのか紹介します。
患者側の観るポイント
バイタル
兎にも角にもまずはバイタルを確認しましょう。
特にCHDFを開始した直後にバイタルは変動しやすいので注意が必要です。
CHDFを開始する前は必ずバイタルを確認しておきましょう。
一言でバイタルといってもたくさんあって具体的になにをみればいいのか分からないと思います。
CHDFの看護において特に注目すべきポイントを以下にまとめます。
1.血圧
先ほども説明した通り、CHDFでは特に開始時に血圧が低下しやすいです。
いま(開始前)は問題ない値でも、CHDFを開始した途端に低下する可能性を考えて、その時の対応手順を事前に医師に確認しておきましょう。
2.心拍数
CHDFに除水を行える様に設定すると、開始直後より徐々に患者さんから水分が抜けていきます。
経過時間と共に除水量が増えていき、水分出納がマイナスバランスに傾いてくると心拍数が上昇していく事があります。
頻脈が続くと患者さんは辛いので、除水量の変更を考慮しましょう。
また水分のマイナスバランスの影響により心拍数が上昇していると言うことは、それだけ血管内のボリュームが不足してきていることも予測する事ができます。
こうなると次は脱血不良が発生しやすくなってくる可能性があるので注意が必要です。
3.CVP(中心静脈圧)
さっきとは逆に除水量が足りず、水分出納がプラスバランスに傾いてくるとCVPが上昇します。
身体に水が溜まり、呼吸に影響が出てくるとSpO2の低下を招く場合もあるので、この様な場合は可能な範囲で除水量の増量を考慮しましょう。
4.体温
CHDF施行中、患者さんの血液は血液回路によって体外へと導かれます。
間接的に血液が外気温にさらされる事となり、冷えた血液は患者さんへ返血されていきます。
この結果として患者さんの体温が低下します。
装置には回路を温める加温器が付属しているので、設定がONになっているか確認しましょう。
ブラッドアクセス
体内の血管と装置の回路をつなぐもの、それがブラッドアクセスです。
透析患者さんが日常的に行っている血液透析(HD)では、主に肘の部分に内シャントと呼ばれる血管吻合部をブラッドアクセスとして血液の脱返血を行います。
集中治療室で行うCHDFでは、内頸静脈または大腿静脈に挿入したダブル(トリプル)ルーメンカテーテルをブラッドアクセスとする場合がほとんどです。
確認しておくポイントとしては、
・挿入の深さ
・カテの向き
・血液回路との接続法
などを観ます。
CHDFは予想しているよりもずっと脱血不良が起きやすいと思っていて下さい。
脱血不良アラームが鳴るとポンプが停止します。
ブラッドアクセスの深さや向きはもちろん、患者さんの体位によっても脱血の具合は変わるので、よく観察しておきましょう。
CHDF開始時に回路と接続したり終了時に回路を切り離したりと、ブラッドアクセスをゴソゴソと触っていて、固定が甘い場合は気づかないうちにカテが引けてしまう事もあるので注意が必要です。
除水量(水分バランス)
集中治療管理をする上で水分バランスの管理はとても大切ですよね。
特にCHDFなどの血液浄化療法では水分バランスが大きく変動するのでしっかり管理しておかなければなりません。
CHDFにおける除水量は、
【除水量=透析液流量ー濾液流量+補液流量】の式で計算できます。
(わざわざ計算しなくてもモニター画面に表示されていますが。)
輸液量、尿量などから計算した患者水分出納バランスにCHDFの除水量も計算に加えて、正確な量を記録に残しておいて下さい。
ACT
ACTとはActivated Coagulation Timeの頭字語で、日本語では活性化凝固時間のことを言い表します。
(Activated Clotting Timeとも言いますが、同じ意味の言葉です。)
そもそも血液は血管内皮細胞以外の物質に触れると凝固していくという性質がありますね。
CHDFにおける血液回路やダイアライザーは血管内皮細胞以外の物質ですので、血液は当然凝固します。
この【血液が凝固するまでにかかる時間】これをACTと呼びます。
ACTの正常値は120秒程度です。
CHDF施行中はヘパリンやナファモスタットメシル酸塩(フサン)といった抗凝固薬を持続的に投与し、ACTを延長します。
しかし抗凝固薬の過剰投与によりACTが延長しすぎてしまうと、今度は出血傾向が強まってしまいます。
CHDF施行中のACTは150〜200秒程度の延長を目指します。
装置側の観るポイント
続いてCHDFの装置側の観るポイントを紹介していきます。
機械が苦手な方にとって装置の部分はハードルが高いと思いますので、なるべくわかりやすく簡潔に説明していきます。
ポンプの流量設定
CHDFでは4つのポンプが稼働します。(抗凝固薬のポンプを含めると5つですね。)
・血液ポンプ
患者さんから血液を脱血し、返血を行うためのポンプ。
流量の単位は他の3つのポンプと異なり[mL/min]である。
血液ポンプの流量を上げると浄化効率は高まるが、脱血不良のリスクも高まる。
・透析液ポンプ
透析液をダイアライザーへ送るためのポンプ。
流量の単位は[mL/hr]。
透析液ポンプの流量を上げると小分子量物質の除去効率が高まる。
ただし、濾液ポンプの流量も併せて上げる必要がある。
もともと透析患者であり日常的に血液透析を行っている患者さんの場合などでは、流量を高めに設定する事がある。
・補液ポンプ
補液をVチャンバーへ送るためのポンプ。
流量の単位は[mL/hr]。
補液ポンプの流量を上げると中分子量物質の除去効率が高まる。
ただし、濾液ポンプの流量も併せて上げる必要がある。
CHDFを行う場合では透析液ポンプの流量とのバランスが大切となる。
・濾液ポンプ
ダイアライザーから透析液や血中の毒素などを引く(除去する)ためのポンプ。
流量の単位は[mL/hr]。
通常濾液ポンプの流量設定は、透析液ポンプの流量設定よりも高く設定する。
除水量の計算式【除水量=透析液流量ー濾液流量+補液流量】からも、濾液流量を高く設定するほど単位時間あたりの除水量が多くなる。
各パートの測定圧
回路図のイラストにもあった通り、CHDFでは回路内のさまざまな圧力を測定しています。
特に重要なのは、
・入口圧(動脈圧)
・返血圧(静脈圧)
・TMP(Trans Membrane Pressure:膜間圧力差)
の3つです。
この3つの圧力は全てメイン(血液)回路に関係する圧力なので、メイン回路のイラストを見直しながら考えてみましょう。

・入口圧(動脈圧)
入口圧はAチャンバーの上に繋がれた圧力計の値を反映している。
入口圧のみが上昇してくると言うことは、Aチャンバーの出口・ダイアライザーの入口・ダイアライザーの内部のどこかに血栓ができ始めている事が考えられる。
圧の上昇を解除できず、上限アラームが鳴り止まない場合は新しいCHDF回路をプライミングし直して、回路ごと交換する。
・返血圧(静脈圧)
返血圧はVチャンバーの上に繋がれた圧力計の値を反映している。
返血圧が上昇してくると言うことは、
・Vチャンバーの出口付近に血栓ができ始めてきている。
・ブラッドアクセスの返血側の先端が血管壁に当たり出口を塞いでいる。
・返血側の血液回路が屈曲してしまっている。
などの事が考えられる。
圧の上昇を解除できず、上限アラームが鳴り止まない場合は新しいCHDF回路をプライミングし直して、回路ごと交換する。
・TMP(膜間圧力差)
TMPは少し難しいかもしれません。
それはTMPの計算式【TMP=(入口圧+返血圧)/ 2 ー濾過圧】をみてもわかる様に、他の所の圧力によって変動するからです。
なので今回はTMPの理屈は置いておいて、こうなったらこう!ということだけを記しておきます。
(機会があればTMPの理屈の解説もしようと思います。)
① TMPと入口圧の両方が明らかに上昇してきている場合
Aチャンバーの出口付近が血栓閉塞しかかっている可能性がある。
② TMP・返血圧・濾過圧の全てが大幅に上昇している場合
Vチャンバーの出口付近が血栓閉塞しかかっている可能性がある。
③ TMPが上昇し、濾過圧が低下してきている場合
ダイアライザー内部にある中空系の側孔が血栓閉塞しかかっている可能性がある。
大切なのは、CHDF開始直後の圧と比べて「徐々に各圧力が上昇してきたのか?」あるいは「突然急上昇したのか?」です。
また個人的に思うことは、入口圧、返血圧、TMP、どの圧力が上昇したとしても、CHDFを継続するには結局回路を丸ごと交換しないといけないので、そんなに難しく考えなくてもいいんじゃないかと思います。
センサーとアラーム
回路図のイラストにもあった通り、CHDFでは回路内のさまざまな箇所にセンサー取り付けています。
センサーの役割をそれぞれ説明します。
・ピロー
脱血不良を感知するためのセンサー。
脱血不良が起こった時ピローは凹んでしまい、この凹みを装置が感知する事で、脱血不良アラームが鳴りポンプが停止する。
対処法として、
・血液ポンプの流量を下げる
・ブラッドアクセスの位置や接続を変えてみる
・除水量を減らす
などの方法をとる。
・気泡センサー(返血側)
Vチャンバーよりも下流にあるセンサー。
血液回路内に気泡を感知すると、気泡検知アラームが鳴りポンプが停止する。
通常この気泡センサーは患者に一番近い部分にあるセンサーなので、患者を守る最後の砦と言える。
対処法として、
・Vチャンバーの液面を確認する
・補液ポンプが空回りしていないか等を確認する
・装置のどこかで血液が漏れていないかを確認す
といった方法をとる。
・気泡センサー(透析液・補液側)
透析液回路と補液回路に取り付け、残りがなくなったことを知らせてくれるセンサー。
それぞれの回路にて透析液の残が無くなり液面が低下した事で気泡を検知するとポンプが停止する。
吊り下げた透析液バッグの重さで検知するタイプのものもある。
・漏血センサー
ダイアライザーの内部には血液の通り道である中空糸と呼ばれる極細の筒が無数にあり、通常ここから血液(血球成分)が漏れ出ることはない。
これが損傷したりダイアライザーそのものが不良品であった場合、血液が中空糸の外に漏れ出る。これを漏血(ろうけつ)と呼ぶ。
漏血は通常濾過チャンバーの付近にある漏血センサーによって発見される。
漏血センサーが正常に作動した場合、ダイアライザーを交換する。
最後に
CHDFについての基本的なことを説明していました。
ちょっと詰め込みすぎて余計に苦手にさせてしまったかも知れませんが、心配しなくても経験をたくさん積めば段々とわかってきます。
私も新人の頃は本当に分からなくて苦労しました。
コチラの教科書がとてもわかりやすかったので、推しておきます。
また、集中治療室で働く方の中には、小児に対するCHDFの担当に就く方もおられると思います。
小児に対するCHDFは成人と違って注意する部分がたくさんあります。
コチラの記事で紹介していますので、ぜひ参考にしていただき、一緒に考えてもらいたいと思います。
うまく説明できていましたか? 参考になった場合は「いいね!」「シェア」「ツイート」などで教えて下さい!

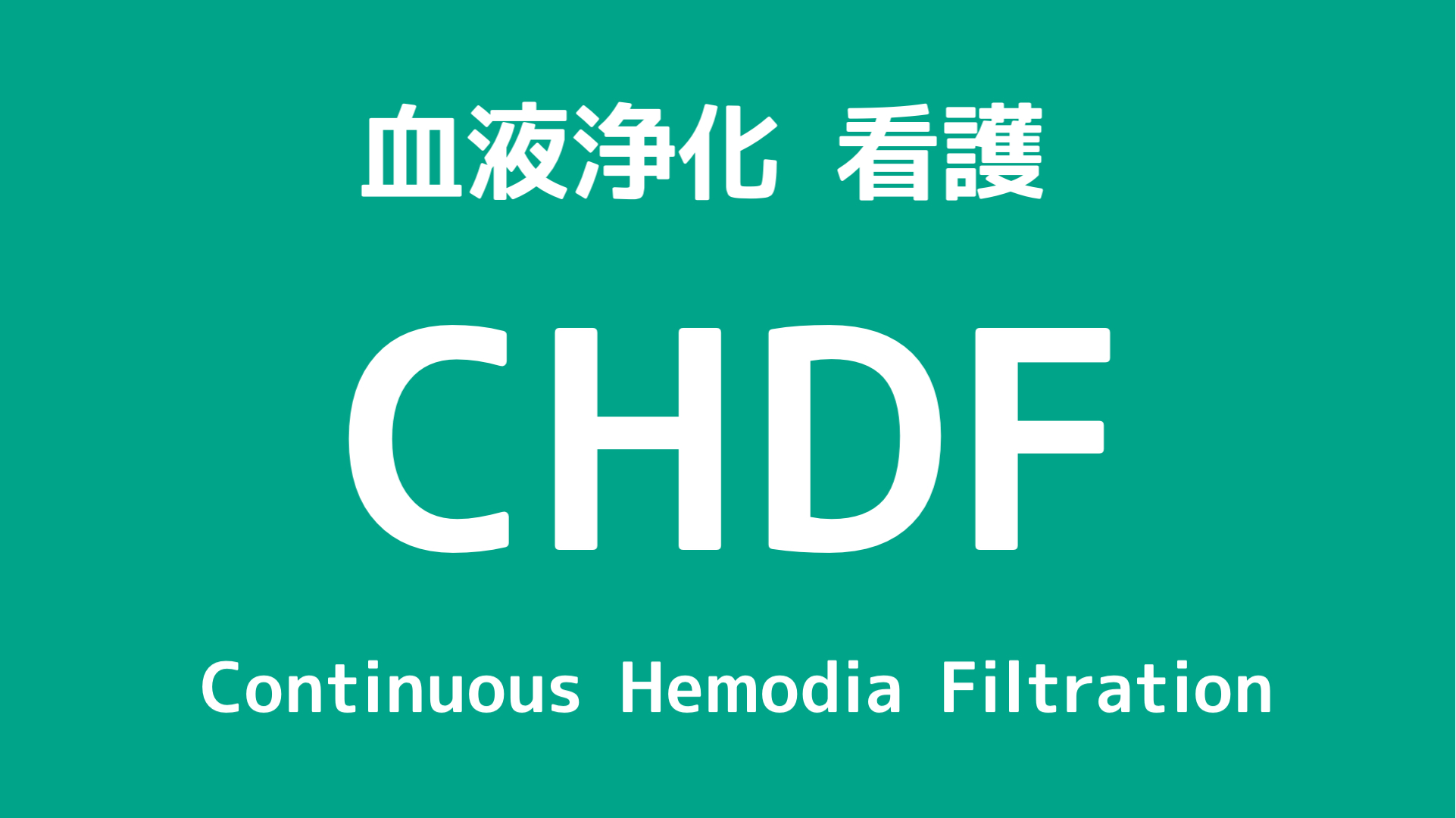





















こんにちは。Twitterもよく拝見しています。
いつも分かりやすいイラストと説明ありがとうございます
今回もイマイチ自分の中でイメージが付きにくいものがあったので、質問させていただきたいです。
除水量=透析液流量ー濾液流量+補液流量
この式なのですが、透析液は補液としても使うと思うのですが、それをどうして引き算にするのでしょうか?また除水量を変更する時には、なんの流量を上げたり下げたりするのかが、いまいちわかってません。わかりにくい質問だったらすみません。教えていただきたいです。
ダイアライザーとVチャンバーに分けて考えてみると分かりやすいと思います。
透析液流量はダイアライザーに入っていく流量で、濾液流量はダイアライザーから出ていく流量です。
そして補液流量はダイアライザーの後にあるVチャンバーに入っていく流量です。
式に書いて下さっているとおり、引き算に使うのは濾液流量だけで合っていますね。
除水量を変更する場合は、水分を抜きたいのか、溶質も除去したいのかで変わってきます。
例えば水分を抜きたいだけならinである透析液流量や補液流量を下げればいいですし、溶質も除去したいならoutの濾液流量を上げます。この辺りの調整は何の目的でCHDFを回しているのかを考えると分かりやすいのかなと思います。