PCPS管理中には必ずと言っていいほどに発生するトラブルの1つであるウェットラング。
ウィットラングが発生すると人工肺でのガス交換効率が悪くなり、高二酸化炭素血症や低酸素血症を引き起こします。
なぜこの様なことが起こるのか、ウェットラングが起こる理由と原因、そしてその対処法としてのO2フラッシュについて解説します。
目次
PCPSの酸素設定について
まずはPCPSの酸素設定について復習しておきます。
PCPSには人工肺があり、これに酸素を流し続けることで血液の酸素化と二酸化炭素の排出を行っています。
この人工肺の設定に対する管理方法は意外にシンプルで、以下の表の通りとなります。

※実際には血液流量との兼ね合いも大切ですね。
ウェットラング発生のメカニズム
人工肺へはガス配管から乾燥した酸素が室温(25℃)で流れ込んでいます。
どのくらい乾燥しているかというと湿度0%です。
人工肺の内部では血液が微小量気化され、これに含まれる僅かな水分は膜を通過して気体相に放出されます。
この時湿度は0%から99%へと変化し、血液温度に加温されます。
その後、人工肺から排気されるガスが室温冷却されることにより水滴となるのです。
これがウェットラングの正体です。

例えるなら、冬の寒い日に部屋の中をヒーターで温め、ついでに加湿もしておくと、中と外の温度差で窓の内側には水滴がついていますよね。これと同じ現象が起こっているのです。
PCPS(ECMO)に発生するトラブルとして代表的なものにプラズマリークがあります。
このトラブルについてのメカニズムについては、コチラの記事を参考にしてみてください。
ウェットラングとガス交換効率の関係
ウェットラングが起こると、人工肺内部の血液の通り道と酸素の通り道を隔てる膜に先程の水滴が付着します。
この水滴が壁となり、血液と酸素の接触を妨げ、血液側への酸素の受け渡し・血液側からの二酸化炭素の排出を妨害します。
その結果、血液中の酸素が低下したり、二酸化炭素が貯留してしまうのです。
ウェットラングが発生した時の対処法としてO2フラッシュを行います。
人工肺の試用期間が長くなってくると、O2フラッシュを行ってもガス交換効率が改善しなくなることもあります。
そうなった場合は、人工肺やPCPS回路をまるごと交換することになります。
O2フラッシュとは
効率の悪いガス交換能のままだと管理が難しくなるので、対処法としてO2フラッシュを行います。
人によっては、そのまんまですが「酸素フラッシュ」と呼ばれることもあります。
これは人工肺内部に溜まった水滴を、高流量の酸素流量で一気に吹き飛ばす作業です。

ただし、これには注意が必要です。
先程の表にもあった様に、酸素流量を増やすとPaCO2は低下します。
O2フラッシュの為とは言え、一時的に酸素流量を上げる事で水滴と一緒に血液中の二酸化炭素も排出されてしまう危険がありる事を意識しておいて下さい。
PaCO2の急激な低下は脳血管を収縮させ、脳血流量を減少させます。
こうなるのを避けるために脳のrSO2をモニタリングしながら慎重にO2フラッシュを行うことをオススメします。
O2フラッシュの方法
人工肺の種類によって、その方法は様々です。
人工肺はたくさんのメーカーから色んな種類のものが販売されています。
その添付文章をよく読んで、推奨される方法で行うのが良いと思います。
あくまで一例ですが、O2フラッシュの方法として、酸素流量10L/minで約1分間維持する と言った方法を取ります。
「血液流量に対して酸素流量は何倍まで」と制限を掛けている種類の人工肺もあります。
小児に対して導入されているPCPS症例では、体格が小さいため血液流量も成人に比べて少ないハズです。
例えばPCPS維持期に血液量1L/min(total)、酸素流量800mL/minの設定の人工肺に対し、O2フラッシュの為とは言え10L/minは流し過ぎな印象です。
フラッシュ時間にもよりますが、最新の注意を払って行って下さい。
ウェットラングの予防対策
常時、酸素流量を高く設定する
ウェットラングとは、人工肺のカス交換膜の孔に結露による水滴が溜まる現象のことでした。
そのタイミングで酸素流量を瞬間的に上げて水滴を吹き飛ばすのがO2フラッシュですが、常時、酸素流量を高く設定しておくことで水滴が溜まりにくくなるという考えです。
ただしこの方法は前述の通り、PaCO2の低下を招くので注意が必要です。
人工肺を温める
人工肺に結露が発生する原因は、人工肺内部の血液相と気相の温度差によるものでした。
この温度差をなくす事ができれば結露の発生を元から予防できます。
具体的には患者体温管理装置(ベアーハガー等)による温風を人工肺に向けて当てます。
私の臨床での経験では、この方法でかなりのウェットラングの発生を抑えることが出来ています。
オススメの教科書
最後にウェットラングについてオススメの教科書を紹介します。
ウェットラングの詳しい説明はもちろん、ECMOの原理、管理法、生理についても詳しく書いてあります。
一見ムズかしそうなタイトルですが、写真やイラスがかなり多く載っていて非常に分かりやすいですよ!
ECMO症例を経験する機会がある方にとってのバイブルとなり得る一冊です。

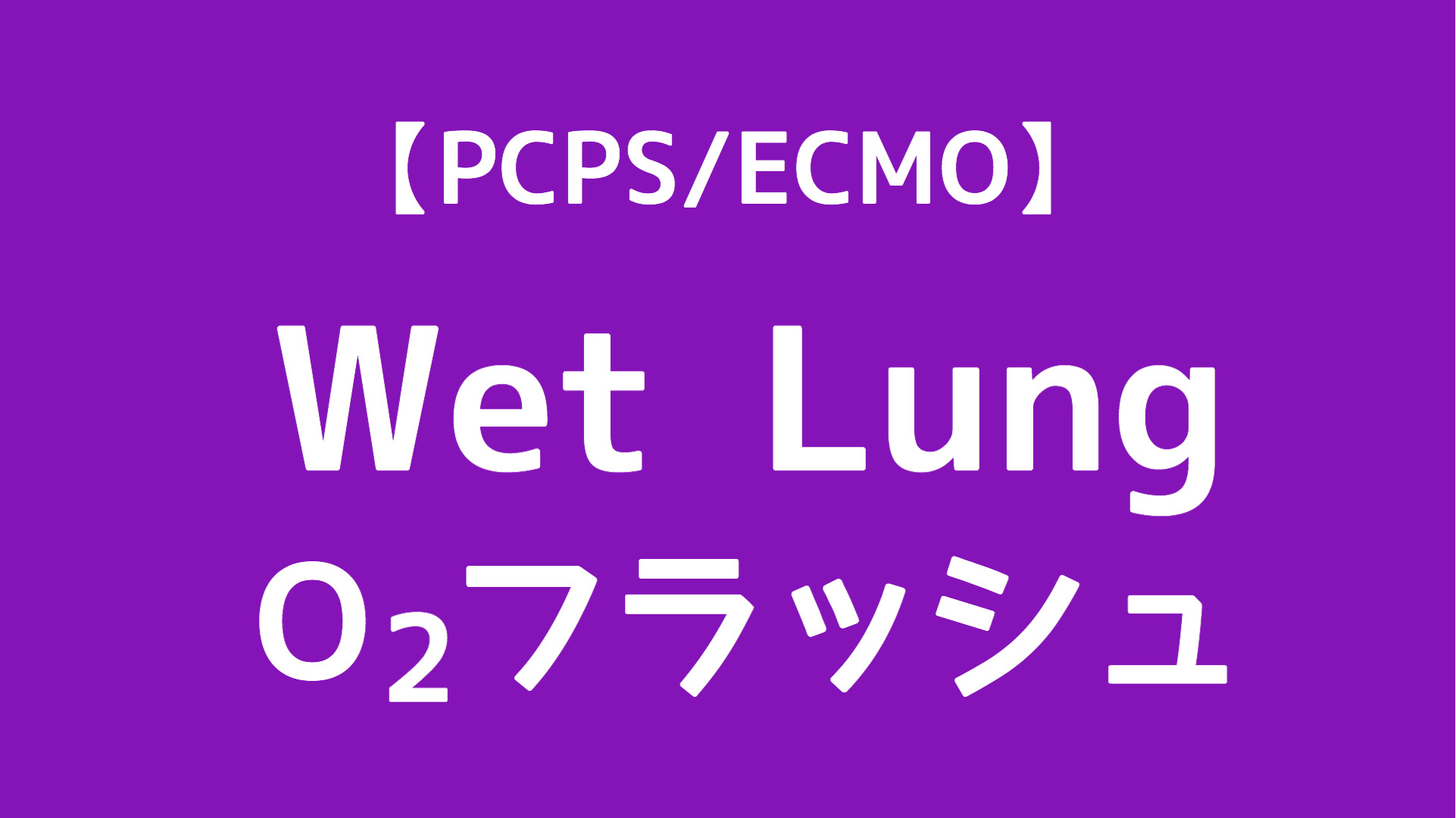




















コメントを残す